人を幸せにする人になろう
- 日々の雑多な感想や記録を書き留めていくことにします―2008年6月~―
1月29日の大阪中央郵便局の緊急シンポに参加しました
◆定員150名のところ、入りきらずに立ち見も出る状態でした。 ◆大阪駅前に高さをそろえて美観地区を作りだそう(高さをそろえる)とした時期の、いまのこる唯一の建物だそうです。建築上、高い評価を受けていると同時に、大阪駅前の都市計画の歴史を伝える
ものでもあるようです。 ◆東京も郵便局会社が収入をえるため、高層ビルを建て、テナントを募集しているようですが、余っている状態で、家賃も相場が下がり、かけた金に対して回収も危ぶまれているとのこと。大阪の場合も、北ヤードを含め駅前の再開発が進む中、1000億円かけて高層ビルを建てても回収できるかきわめてあやしいとのことです。そうした構想がなお揺れ動いていることは、解体を急ぎながら、3年間は空閑地として遊ばしておくというところにも表れているようです。 ◆集会では、味わいある建築物をリニューアルして成功している例も紹介されていました。残す範囲が狭すぎる(東京は解体が始まってからの運動で保存範囲が当初の倍になったとのことです)、ということかと漠然と考えてきましたが、丸ごと残して50億円くらいで改修して、魅力を作りだす方がはるかに危険がなく現実的だ、という主張は説得力がありました。
和泉国府はどこなのか
◆1月21日に、いずみの国歴史館で、市史テーマ編考古チームの研究会。もう5月に原稿〆切という間際になっ て、やっとこさスタート。古代や中世はとっくに一巡。
て、やっとこさスタート。古代や中世はとっくに一巡。
◆しょっぱなは、乾さんの弥生の話と、千葉君の陶邑の話。乾さんの弥生中期から後期のイメージは、オレのものに近いのだが、そのあたりを思いっきり書いて欲しいものである。大野池が干上がったら、窯跡はたくさん出てくるのだろうか。大野池はいつできたか。へたすりゃ5世紀後半と思っているが、これは項目を改めよう。
◆この時に、府中を掘っても古代の遺構が当たらず、中世やと。それに対して、大園では、ごっつい柱の建物が見つかり、また井戸も?、大園はすごいと。そうかもしれません、よく知らないんですが・・・。ぜんぜん伝わってこないのですが、それは、まあこっちの怠慢?
◆だが、府中はほんとにダメなのか。どこをどれだけ掘ったのか、そういうこともわからないのだが・・・。確かに現在の府中には正方位地割は顕著でなく、和泉寺周辺が中心だが、それでも一定の広がりがあるのだが。南海道も考えなあかん。
◆和泉寺の東側は、和泉郡家も考えとかなあかんかもしれない。
◆しょっぱなは、乾さんの弥生の話と、千葉君の陶邑の話。乾さんの弥生中期から後期のイメージは、オレのものに近いのだが、そのあたりを思いっきり書いて欲しいものである。大野池が干上がったら、窯跡はたくさん出てくるのだろうか。大野池はいつできたか。へたすりゃ5世紀後半と思っているが、これは項目を改めよう。
◆この時に、府中を掘っても古代の遺構が当たらず、中世やと。それに対して、大園では、ごっつい柱の建物が見つかり、また井戸も?、大園はすごいと。そうかもしれません、よく知らないんですが・・・。ぜんぜん伝わってこないのですが、それは、まあこっちの怠慢?
◆だが、府中はほんとにダメなのか。どこをどれだけ掘ったのか、そういうこともわからないのだが・・・。確かに現在の府中には正方位地割は顕著でなく、和泉寺周辺が中心だが、それでも一定の広がりがあるのだが。南海道も考えなあかん。
◆和泉寺の東側は、和泉郡家も考えとかなあかんかもしれない。
酒船石遺跡
◆酒船石遺跡。南からでなく、例の亀形石側から酒船石めざして丘陵を上がると、途中に、石上の凝灰岩?(砂 岩?)を積み上げた石垣遺構が露出展示してある。知らんかった。
岩?)を積み上げた石垣遺構が露出展示してある。知らんかった。
◆双槻宮はやはり多武峰とみるべきで、この石垣たちで囲まる酒船石遺跡は別物という。これって何だろうか。山城ちゃうんか、と思いますよね。が、高安城に比べればぜんぜん低く、そもそも飛鳥まで攻め込まれたら、もう終わってるだろう。背後の逃げ城にしては低いわな。ま、いずれにしても、すごい遺跡なんだが、いったいぜんたいどこまで分かっているのだろうか。確認調査をいけるところまでやって欲しいものだが・・・。そして、目立つ部分で、多重構造がわかるような、一定の範囲でいいから復元的な整備をしてやるとカッコいいのだが。
◆どうなんでしょうね、奈文研・奈良県・橿原市そして明日香村が、連携して調査や整備を進めるといった体制はとれないものか。もっともっと整備せよというのではないし、遅いというつもりもないけれど、ベクトルがぜんぶ違う方向なのだとすると、ちょっとね~。
◆双槻宮はやはり多武峰とみるべきで、この石垣たちで囲まる酒船石遺跡は別物という。これって何だろうか。山城ちゃうんか、と思いますよね。が、高安城に比べればぜんぜん低く、そもそも飛鳥まで攻め込まれたら、もう終わってるだろう。背後の逃げ城にしては低いわな。ま、いずれにしても、すごい遺跡なんだが、いったいぜんたいどこまで分かっているのだろうか。確認調査をいけるところまでやって欲しいものだが・・・。そして、目立つ部分で、多重構造がわかるような、一定の範囲でいいから復元的な整備をしてやるとカッコいいのだが。
◆どうなんでしょうね、奈文研・奈良県・橿原市そして明日香村が、連携して調査や整備を進めるといった体制はとれないものか。もっともっと整備せよというのではないし、遅いというつもりもないけれど、ベクトルがぜんぶ違う方向なのだとすると、ちょっとね~。
カナヅカ古墳
◆1月30日、今日から『和泉郡の条里』にむけてスクランブル体制、とはいえ、週2くらいですけど。濱道君にまか せきりで、ほとんどほったらかしで、ファイルが全然整理されていなかったものを整理し、インデザインのリンクを更新し、打ち出した。図版の前の頁割り図も木建さんに作ってもらう。あと1ヶ月で決着つけよう。
せきりで、ほとんどほったらかしで、ファイルが全然整理されていなかったものを整理し、インデザインのリンクを更新し、打ち出した。図版の前の頁割り図も木建さんに作ってもらう。あと1ヶ月で決着つけよう。
◆神明山のリーフレットが納品されました。
◆いま31日の午前3時、眠くて寝ようとしたが、風呂にはいるとまた少し覚醒したのでブログを書くことに。で、12月17日の飛鳥。カナヅカ。ぜんぜんそれまで意識したことがなかったが、だいぶ浸食されているとはいえ、それでもけっこうなマウンドを保っていますね。通りがかりで写真を撮っただけで、接近しなかったが・・・。鬼の雪隠・俎に行くことがあれば、そのすぐ西側ですので、訪ねてみてください。
◆神明山のリーフレットが納品されました。
◆いま31日の午前3時、眠くて寝ようとしたが、風呂にはいるとまた少し覚醒したのでブログを書くことに。で、12月17日の飛鳥。カナヅカ。ぜんぜんそれまで意識したことがなかったが、だいぶ浸食されているとはいえ、それでもけっこうなマウンドを保っていますね。通りがかりで写真を撮っただけで、接近しなかったが・・・。鬼の雪隠・俎に行くことがあれば、そのすぐ西側ですので、訪ねてみてください。
緊急シンポジウム 大阪中央郵便局
◆遅くなってしまいました。明日、開催される緊急シンポジウムです。
http://ocpo-1939.blogspot.com/
大阪中央郵便局とこれからの大阪を考える―局舎の解体報道をうけて―
http://ocpo-1939.blogspot.com/
大阪中央郵便局とこれからの大阪を考える―局舎の解体報道をうけて―
◎参加費 500円(資料代を含む)
◎定 員 150名(申込み不要 当日先着順)
◎主 催 大阪中央郵便局を守る会
◎主 催 大阪中央郵便局を守る会
◎後 援 DOCOMOMO Japan 近畿産業考古学会(KINIAS)/日本建築学会近畿支部(予定)/日本建築家協会(JIA)近畿支部(予定)
◎問合せ先 大阪中央郵便局を守る会 事務局 メール:osaka1939@s-takaoka.net
◎発言者
長山雅一(流通科学大学名誉教授,「大阪中央郵便局を守る会」代表)/橋爪紳也(建築史家,大阪府立大学教授)/南一誠 (芝浦工業大学教授・学長補佐,日本学術会議連携会員)/松隈洋 (建築史家,京都工芸繊維大学教授)/高岡伸一(建築家,大阪市立大学特任講師,大阪中央郵便局を守る会」事務局長)/倉方俊輔(建築史家,大阪市立大学准教授)/司会(発言者は事情により変更となることがあります)
神明山のリーフ、もうすぐ納品されると思います
◆校正刷りではなく、原稿の画像だが、アップしておきます。
◆考古学ジャーナルに佐紀の墳丘を書けと依頼されて、ごくごく簡単な一文を出しましたが、このたび発行さ れました。
れました。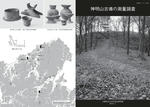
◆たつの市の三角縁神獣鏡の資料紹介原稿、本日(1月28日)、ようやく完成し、日本考古学会へ送付しました。写真の掲載許可取らな・・・
◆ヒストリア2月号に、11月から1月にかけて実施された、郡山新木山・大仙・上石津ミサンザイ・広陵新木山・向墓山の、宮内庁関係の見学会報告を、関大の大学院生、それと北山さんと連名で報告しますが、それも校正にかかっています。
◆鏡、現在の打ち出しを下垣さんに送り、順番の並べ替えを依頼しました。そういえば、彼は『倭製鏡一覧』というのを刊行しており、鏡名などはそっちを見てくれと。取り出してきて見たが、まあマニアってあんなもんでしょうが、たいへんな労作です、「ようやるわ」。
◆条里、いままでの進捗を確認、小字調べのヌケを和泉市教委に依頼。うちの学生を投入しバイトを増強し、2月はスクランブル体制で入稿にむかって作業を進める予定。条里の原稿を書くために、金田さんの本を3冊購入、郷(里)は領域である、という前から書きかけている原稿もそこに投入する予定。さて1ヶ月で完成するでしょうか。
◆天理大学に依頼していた大阪城のレーダー探査も、桑原さんから正式に回答をいただき、GO。もうひとつ城関係のプランニングがあるのだが、その計画書を書き上げようとしてはや3週間、いまから原案を作り上げてしまうところまでいく予定。
◆たつの市の三角縁神獣鏡の資料紹介原稿、本日(1月28日)、ようやく完成し、日本考古学会へ送付しました。写真の掲載許可取らな・・・
◆ヒストリア2月号に、11月から1月にかけて実施された、郡山新木山・大仙・上石津ミサンザイ・広陵新木山・向墓山の、宮内庁関係の見学会報告を、関大の大学院生、それと北山さんと連名で報告しますが、それも校正にかかっています。
◆鏡、現在の打ち出しを下垣さんに送り、順番の並べ替えを依頼しました。そういえば、彼は『倭製鏡一覧』というのを刊行しており、鏡名などはそっちを見てくれと。取り出してきて見たが、まあマニアってあんなもんでしょうが、たいへんな労作です、「ようやるわ」。
◆条里、いままでの進捗を確認、小字調べのヌケを和泉市教委に依頼。うちの学生を投入しバイトを増強し、2月はスクランブル体制で入稿にむかって作業を進める予定。条里の原稿を書くために、金田さんの本を3冊購入、郷(里)は領域である、という前から書きかけている原稿もそこに投入する予定。さて1ヶ月で完成するでしょうか。
◆天理大学に依頼していた大阪城のレーダー探査も、桑原さんから正式に回答をいただき、GO。もうひとつ城関係のプランニングがあるのだが、その計画書を書き上げようとしてはや3週間、いまから原案を作り上げてしまうところまでいく予定。
タテツキと石塚
◆3月下旬に佐倉・歴博の研究会で共同研究の報告書の骨子案を発表せねばならない。ま、古墳時代の始 まりの話をすることになりそうだ。前に「古墳時代の暦年代」というので、膨大な資料を作り発表したが、C14の新年代のデータで弥生時代をどう考えていくかというものに、数人、古墳時代の人間が組み込まれており、庄内やら布留0あたりの話に絞った方がいいだろう。
まりの話をすることになりそうだ。前に「古墳時代の暦年代」というので、膨大な資料を作り発表したが、C14の新年代のデータで弥生時代をどう考えていくかというものに、数人、古墳時代の人間が組み込まれており、庄内やら布留0あたりの話に絞った方がいいだろう。
◆で、タテツキと石塚を考えているのだが、タテツキが先行するとしてどれくらいですかね。石塚の時期も揺れがあるが・・・。へたしたら20年くらいに過ぎない?。どんなもんか。
◆タテツキは吉備の弥生後期社会の到達点ですよね。これまでにない墳墓を築造しようとしたと。が、先行する円形墓はあっても、主流は吉備でも方形墓である。後続する鯉喰も方形だ。タテツキは、吉備のなかだけでは生まれないのでは。どうやったら、あんなものが生まれるのか。大久保さん曰く、周辺諸地域の先行する墳墓要素を取り込んで造られたのではないかとのこと。ほかにはないものをということで、円!、となったのか。
◆で、纒向石塚である。現状で、タテツキが先行する。タテツキの双方の一方を取れば前方後円墳になる、石塚が説明できる。ま、それはそうだ。
◆問題はしかし解釈はいろいろありうる。(1)実は畿内の弥生社会のなかで前方後円墳に至る前史があって、そのなかで石塚が生まれた。「石塚の前あり説」(2)畿内社会が、吉備がタテツキを生み出したように、独自に畿内が石塚を創出した。「石塚創出説」(3)吉備のタテツキの影響を強く受けて畿内が造った。(4)吉備勢力が造った、ないし、東部瀬戸内勢力が造った。ともかくも、吉備の関わりをどうみるか・・・。タテツキの創出と同じように畿内で創出されたのか、吉備の直の影響を認めるのか。
◆石塚のあとは、吉備でタテツキ後が継続しないのと違って、勝山とかマキムク型前方後円墳が続き定着を見せるので、3世紀前半以降の各地でポツポツ見られる前方後円系のものは、畿内墓制の影響で(地域での展開があるにせよ)いちおう説明づけることができる(萩原も鶴尾も)
◆実におおまかな整理ですが、なので、箸墓より前かといった議論は、纒向諸墳の調査の進展によりあんまり問題ではなくなっている。現状の起点である石塚(2世紀末頃らしい)、これがどのように生まれたのか、どう脈絡づけ説明できるのかが現時点の課題だろう。
◆庄内式=纒向が2世紀後半にはさかのぼりそうなので、纒向は、倭国乱の前には形成を開始しており、それは畿内弥生後期社会のひとつの帰結と考えています。その近傍にヤマト王墓が造られるのは当たり前。だけど、それ以前、まだ大和の環濠集落が残存している段階でも、第Ⅴ様式に斉一化し銅鐸を造って周辺に働きかける主体は既にできあがっていて、その主導勢力がいたはずだ。石塚以前にも墳墓は当然あったであろう、と。吉備のように丘陵などがポツポツあるわけではなく、河内や奈良盆地の平野を生活基盤とする畿内においては、集落近傍の平地に造ってあるだろう。まだ見つかっていないだけ・・・、はっきりそう思います。
◆それが前方後円墳につながるようなものかどうかはわからないわけですが、ありうるとみておきたいと思います。
◆で、タテツキと石塚を考えているのだが、タテツキが先行するとしてどれくらいですかね。石塚の時期も揺れがあるが・・・。へたしたら20年くらいに過ぎない?。どんなもんか。
◆タテツキは吉備の弥生後期社会の到達点ですよね。これまでにない墳墓を築造しようとしたと。が、先行する円形墓はあっても、主流は吉備でも方形墓である。後続する鯉喰も方形だ。タテツキは、吉備のなかだけでは生まれないのでは。どうやったら、あんなものが生まれるのか。大久保さん曰く、周辺諸地域の先行する墳墓要素を取り込んで造られたのではないかとのこと。ほかにはないものをということで、円!、となったのか。
◆で、纒向石塚である。現状で、タテツキが先行する。タテツキの双方の一方を取れば前方後円墳になる、石塚が説明できる。ま、それはそうだ。
◆問題はしかし解釈はいろいろありうる。(1)実は畿内の弥生社会のなかで前方後円墳に至る前史があって、そのなかで石塚が生まれた。「石塚の前あり説」(2)畿内社会が、吉備がタテツキを生み出したように、独自に畿内が石塚を創出した。「石塚創出説」(3)吉備のタテツキの影響を強く受けて畿内が造った。(4)吉備勢力が造った、ないし、東部瀬戸内勢力が造った。ともかくも、吉備の関わりをどうみるか・・・。タテツキの創出と同じように畿内で創出されたのか、吉備の直の影響を認めるのか。
◆石塚のあとは、吉備でタテツキ後が継続しないのと違って、勝山とかマキムク型前方後円墳が続き定着を見せるので、3世紀前半以降の各地でポツポツ見られる前方後円系のものは、畿内墓制の影響で(地域での展開があるにせよ)いちおう説明づけることができる(萩原も鶴尾も)
◆実におおまかな整理ですが、なので、箸墓より前かといった議論は、纒向諸墳の調査の進展によりあんまり問題ではなくなっている。現状の起点である石塚(2世紀末頃らしい)、これがどのように生まれたのか、どう脈絡づけ説明できるのかが現時点の課題だろう。
◆庄内式=纒向が2世紀後半にはさかのぼりそうなので、纒向は、倭国乱の前には形成を開始しており、それは畿内弥生後期社会のひとつの帰結と考えています。その近傍にヤマト王墓が造られるのは当たり前。だけど、それ以前、まだ大和の環濠集落が残存している段階でも、第Ⅴ様式に斉一化し銅鐸を造って周辺に働きかける主体は既にできあがっていて、その主導勢力がいたはずだ。石塚以前にも墳墓は当然あったであろう、と。吉備のように丘陵などがポツポツあるわけではなく、河内や奈良盆地の平野を生活基盤とする畿内においては、集落近傍の平地に造ってあるだろう。まだ見つかっていないだけ・・・、はっきりそう思います。
◆それが前方後円墳につながるようなものかどうかはわからないわけですが、ありうるとみておきたいと思います。
プラグイン
カレンダー
カテゴリー
フリーエリア
最新コメント
最新記事
(02/05)
(02/05)
(01/27)
(01/16)
(01/13)
最新トラックバック
プロフィール
HN:
雲楽
年齢:
60
性別:
男性
誕生日:
1964/03/22
職業:
大学教員
自己紹介:
兵庫県加古川市生まれ。高校時代に考古学を志す。京都大学に学び、その後、奈良国立文化財研究所勤務。文化庁記念物課を経て、現在、大阪の大学教員やってます。血液型A型。大阪府柏原市在住。