人を幸せにする人になろう
- 日々の雑多な感想や記録を書き留めていくことにします―2008年6月~―
緊急シンポジウム 大阪中央郵便局
◆遅くなってしまいました。明日、開催される緊急シンポジウムです。
http://ocpo-1939.blogspot.com/
大阪中央郵便局とこれからの大阪を考える―局舎の解体報道をうけて―
http://ocpo-1939.blogspot.com/
大阪中央郵便局とこれからの大阪を考える―局舎の解体報道をうけて―
◎参加費 500円(資料代を含む)
◎定 員 150名(申込み不要 当日先着順)
◎主 催 大阪中央郵便局を守る会
◎主 催 大阪中央郵便局を守る会
◎後 援 DOCOMOMO Japan 近畿産業考古学会(KINIAS)/日本建築学会近畿支部(予定)/日本建築家協会(JIA)近畿支部(予定)
◎問合せ先 大阪中央郵便局を守る会 事務局 メール:osaka1939@s-takaoka.net
◎発言者
長山雅一(流通科学大学名誉教授,「大阪中央郵便局を守る会」代表)/橋爪紳也(建築史家,大阪府立大学教授)/南一誠 (芝浦工業大学教授・学長補佐,日本学術会議連携会員)/松隈洋 (建築史家,京都工芸繊維大学教授)/高岡伸一(建築家,大阪市立大学特任講師,大阪中央郵便局を守る会」事務局長)/倉方俊輔(建築史家,大阪市立大学准教授)/司会(発言者は事情により変更となることがあります)
神明山のリーフ、もうすぐ納品されると思います
◆校正刷りではなく、原稿の画像だが、アップしておきます。
◆考古学ジャーナルに佐紀の墳丘を書けと依頼されて、ごくごく簡単な一文を出しましたが、このたび発行さ れました。
れました。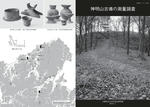
◆たつの市の三角縁神獣鏡の資料紹介原稿、本日(1月28日)、ようやく完成し、日本考古学会へ送付しました。写真の掲載許可取らな・・・
◆ヒストリア2月号に、11月から1月にかけて実施された、郡山新木山・大仙・上石津ミサンザイ・広陵新木山・向墓山の、宮内庁関係の見学会報告を、関大の大学院生、それと北山さんと連名で報告しますが、それも校正にかかっています。
◆鏡、現在の打ち出しを下垣さんに送り、順番の並べ替えを依頼しました。そういえば、彼は『倭製鏡一覧』というのを刊行しており、鏡名などはそっちを見てくれと。取り出してきて見たが、まあマニアってあんなもんでしょうが、たいへんな労作です、「ようやるわ」。
◆条里、いままでの進捗を確認、小字調べのヌケを和泉市教委に依頼。うちの学生を投入しバイトを増強し、2月はスクランブル体制で入稿にむかって作業を進める予定。条里の原稿を書くために、金田さんの本を3冊購入、郷(里)は領域である、という前から書きかけている原稿もそこに投入する予定。さて1ヶ月で完成するでしょうか。
◆天理大学に依頼していた大阪城のレーダー探査も、桑原さんから正式に回答をいただき、GO。もうひとつ城関係のプランニングがあるのだが、その計画書を書き上げようとしてはや3週間、いまから原案を作り上げてしまうところまでいく予定。
◆たつの市の三角縁神獣鏡の資料紹介原稿、本日(1月28日)、ようやく完成し、日本考古学会へ送付しました。写真の掲載許可取らな・・・
◆ヒストリア2月号に、11月から1月にかけて実施された、郡山新木山・大仙・上石津ミサンザイ・広陵新木山・向墓山の、宮内庁関係の見学会報告を、関大の大学院生、それと北山さんと連名で報告しますが、それも校正にかかっています。
◆鏡、現在の打ち出しを下垣さんに送り、順番の並べ替えを依頼しました。そういえば、彼は『倭製鏡一覧』というのを刊行しており、鏡名などはそっちを見てくれと。取り出してきて見たが、まあマニアってあんなもんでしょうが、たいへんな労作です、「ようやるわ」。
◆条里、いままでの進捗を確認、小字調べのヌケを和泉市教委に依頼。うちの学生を投入しバイトを増強し、2月はスクランブル体制で入稿にむかって作業を進める予定。条里の原稿を書くために、金田さんの本を3冊購入、郷(里)は領域である、という前から書きかけている原稿もそこに投入する予定。さて1ヶ月で完成するでしょうか。
◆天理大学に依頼していた大阪城のレーダー探査も、桑原さんから正式に回答をいただき、GO。もうひとつ城関係のプランニングがあるのだが、その計画書を書き上げようとしてはや3週間、いまから原案を作り上げてしまうところまでいく予定。
タテツキと石塚
◆3月下旬に佐倉・歴博の研究会で共同研究の報告書の骨子案を発表せねばならない。ま、古墳時代の始 まりの話をすることになりそうだ。前に「古墳時代の暦年代」というので、膨大な資料を作り発表したが、C14の新年代のデータで弥生時代をどう考えていくかというものに、数人、古墳時代の人間が組み込まれており、庄内やら布留0あたりの話に絞った方がいいだろう。
まりの話をすることになりそうだ。前に「古墳時代の暦年代」というので、膨大な資料を作り発表したが、C14の新年代のデータで弥生時代をどう考えていくかというものに、数人、古墳時代の人間が組み込まれており、庄内やら布留0あたりの話に絞った方がいいだろう。
◆で、タテツキと石塚を考えているのだが、タテツキが先行するとしてどれくらいですかね。石塚の時期も揺れがあるが・・・。へたしたら20年くらいに過ぎない?。どんなもんか。
◆タテツキは吉備の弥生後期社会の到達点ですよね。これまでにない墳墓を築造しようとしたと。が、先行する円形墓はあっても、主流は吉備でも方形墓である。後続する鯉喰も方形だ。タテツキは、吉備のなかだけでは生まれないのでは。どうやったら、あんなものが生まれるのか。大久保さん曰く、周辺諸地域の先行する墳墓要素を取り込んで造られたのではないかとのこと。ほかにはないものをということで、円!、となったのか。
◆で、纒向石塚である。現状で、タテツキが先行する。タテツキの双方の一方を取れば前方後円墳になる、石塚が説明できる。ま、それはそうだ。
◆問題はしかし解釈はいろいろありうる。(1)実は畿内の弥生社会のなかで前方後円墳に至る前史があって、そのなかで石塚が生まれた。「石塚の前あり説」(2)畿内社会が、吉備がタテツキを生み出したように、独自に畿内が石塚を創出した。「石塚創出説」(3)吉備のタテツキの影響を強く受けて畿内が造った。(4)吉備勢力が造った、ないし、東部瀬戸内勢力が造った。ともかくも、吉備の関わりをどうみるか・・・。タテツキの創出と同じように畿内で創出されたのか、吉備の直の影響を認めるのか。
◆石塚のあとは、吉備でタテツキ後が継続しないのと違って、勝山とかマキムク型前方後円墳が続き定着を見せるので、3世紀前半以降の各地でポツポツ見られる前方後円系のものは、畿内墓制の影響で(地域での展開があるにせよ)いちおう説明づけることができる(萩原も鶴尾も)
◆実におおまかな整理ですが、なので、箸墓より前かといった議論は、纒向諸墳の調査の進展によりあんまり問題ではなくなっている。現状の起点である石塚(2世紀末頃らしい)、これがどのように生まれたのか、どう脈絡づけ説明できるのかが現時点の課題だろう。
◆庄内式=纒向が2世紀後半にはさかのぼりそうなので、纒向は、倭国乱の前には形成を開始しており、それは畿内弥生後期社会のひとつの帰結と考えています。その近傍にヤマト王墓が造られるのは当たり前。だけど、それ以前、まだ大和の環濠集落が残存している段階でも、第Ⅴ様式に斉一化し銅鐸を造って周辺に働きかける主体は既にできあがっていて、その主導勢力がいたはずだ。石塚以前にも墳墓は当然あったであろう、と。吉備のように丘陵などがポツポツあるわけではなく、河内や奈良盆地の平野を生活基盤とする畿内においては、集落近傍の平地に造ってあるだろう。まだ見つかっていないだけ・・・、はっきりそう思います。
◆それが前方後円墳につながるようなものかどうかはわからないわけですが、ありうるとみておきたいと思います。
◆で、タテツキと石塚を考えているのだが、タテツキが先行するとしてどれくらいですかね。石塚の時期も揺れがあるが・・・。へたしたら20年くらいに過ぎない?。どんなもんか。
◆タテツキは吉備の弥生後期社会の到達点ですよね。これまでにない墳墓を築造しようとしたと。が、先行する円形墓はあっても、主流は吉備でも方形墓である。後続する鯉喰も方形だ。タテツキは、吉備のなかだけでは生まれないのでは。どうやったら、あんなものが生まれるのか。大久保さん曰く、周辺諸地域の先行する墳墓要素を取り込んで造られたのではないかとのこと。ほかにはないものをということで、円!、となったのか。
◆で、纒向石塚である。現状で、タテツキが先行する。タテツキの双方の一方を取れば前方後円墳になる、石塚が説明できる。ま、それはそうだ。
◆問題はしかし解釈はいろいろありうる。(1)実は畿内の弥生社会のなかで前方後円墳に至る前史があって、そのなかで石塚が生まれた。「石塚の前あり説」(2)畿内社会が、吉備がタテツキを生み出したように、独自に畿内が石塚を創出した。「石塚創出説」(3)吉備のタテツキの影響を強く受けて畿内が造った。(4)吉備勢力が造った、ないし、東部瀬戸内勢力が造った。ともかくも、吉備の関わりをどうみるか・・・。タテツキの創出と同じように畿内で創出されたのか、吉備の直の影響を認めるのか。
◆石塚のあとは、吉備でタテツキ後が継続しないのと違って、勝山とかマキムク型前方後円墳が続き定着を見せるので、3世紀前半以降の各地でポツポツ見られる前方後円系のものは、畿内墓制の影響で(地域での展開があるにせよ)いちおう説明づけることができる(萩原も鶴尾も)
◆実におおまかな整理ですが、なので、箸墓より前かといった議論は、纒向諸墳の調査の進展によりあんまり問題ではなくなっている。現状の起点である石塚(2世紀末頃らしい)、これがどのように生まれたのか、どう脈絡づけ説明できるのかが現時点の課題だろう。
◆庄内式=纒向が2世紀後半にはさかのぼりそうなので、纒向は、倭国乱の前には形成を開始しており、それは畿内弥生後期社会のひとつの帰結と考えています。その近傍にヤマト王墓が造られるのは当たり前。だけど、それ以前、まだ大和の環濠集落が残存している段階でも、第Ⅴ様式に斉一化し銅鐸を造って周辺に働きかける主体は既にできあがっていて、その主導勢力がいたはずだ。石塚以前にも墳墓は当然あったであろう、と。吉備のように丘陵などがポツポツあるわけではなく、河内や奈良盆地の平野を生活基盤とする畿内においては、集落近傍の平地に造ってあるだろう。まだ見つかっていないだけ・・・、はっきりそう思います。
◆それが前方後円墳につながるようなものかどうかはわからないわけですが、ありうるとみておきたいと思います。
ブログもおもろい
◆年末だったか、年始だったか、あるブログにはまって、ずっと見ていた。いまもブックマークして見ている。基本的に毎日、更新される。仕事から23時過ぎに帰ってきて、それから食事をして、ブログを更新するのだとか。
◆まあ、どんなブログかは隠しておこう。世の中にはいろんな人がいるということを知ることができる。また本をとにかく読んでいる。ガンガン、アマゾンで注文して、1日1冊読んでんじゃねえか、というペースである。実に雑多であることもオモシロイ。本業のこと、地元のこと、食べ物のこと、男のこと。書評。知っている人は知っているんだろうが、身の回りの人も案外知らないのかもしれません。オレのブログは、最初、なんの作法も知らず自分の名前をタイトルにつけていて、いまはそうでないわけだが、名前で検索すると、このブログが出てきてしまう。別に隠すことでもないし、困りはしませんが。見ていたブログというやつは、まあ、ちょっと中身が・・・、というもので、職場とか近所とか心配するのだが、ほとんど特定されることなくバレてないのかもしれない。
◆だからこそ書ける、というのもあるんでしょうね。なんかそういうギャップがオモシロイわけだ。すべてが本音トークなわけだが、ちゃんとした職業人なわけで、そういうネタと下半身のネタがまぜまぜになっているわけだ。それがトータルで人間だ、みたいな感動を覚える。
◆オレは、自分が誰かバレバレなので、まずいネタは書きません。カミさんにも見られているので、やばい話はいたしません(ま、ないし・・・)。なので、すべてをさらけ出してはいません、割とふつ~の内容です。ま、行動はだいたいチェックできるでしょうか。年末も、文学部事務室が探していたらしく、携帯に電話が何度も入っていたのですが、集中講義中だったし、掛け返しませんでした(ごめんなさい)。何の電話だったかというと、まあ〆切のあることをやってなかったということで、それは1月4日にクリアしたわけですが、「ブログで仙台にいるところまでは突き止めたんですが」と言われてしまいました(出発前のばたばたで出張届を出してませんでした)。何をやっているかは、バレバレですね。
◆といわけで、カミさんと子供2人、計3人がコタツに入ってグ~グ~寝ていて、つまらないので、つまらない記事を書いてしまいました。
◆まあ、どんなブログかは隠しておこう。世の中にはいろんな人がいるということを知ることができる。また本をとにかく読んでいる。ガンガン、アマゾンで注文して、1日1冊読んでんじゃねえか、というペースである。実に雑多であることもオモシロイ。本業のこと、地元のこと、食べ物のこと、男のこと。書評。知っている人は知っているんだろうが、身の回りの人も案外知らないのかもしれません。オレのブログは、最初、なんの作法も知らず自分の名前をタイトルにつけていて、いまはそうでないわけだが、名前で検索すると、このブログが出てきてしまう。別に隠すことでもないし、困りはしませんが。見ていたブログというやつは、まあ、ちょっと中身が・・・、というもので、職場とか近所とか心配するのだが、ほとんど特定されることなくバレてないのかもしれない。
◆だからこそ書ける、というのもあるんでしょうね。なんかそういうギャップがオモシロイわけだ。すべてが本音トークなわけだが、ちゃんとした職業人なわけで、そういうネタと下半身のネタがまぜまぜになっているわけだ。それがトータルで人間だ、みたいな感動を覚える。
◆オレは、自分が誰かバレバレなので、まずいネタは書きません。カミさんにも見られているので、やばい話はいたしません(ま、ないし・・・)。なので、すべてをさらけ出してはいません、割とふつ~の内容です。ま、行動はだいたいチェックできるでしょうか。年末も、文学部事務室が探していたらしく、携帯に電話が何度も入っていたのですが、集中講義中だったし、掛け返しませんでした(ごめんなさい)。何の電話だったかというと、まあ〆切のあることをやってなかったということで、それは1月4日にクリアしたわけですが、「ブログで仙台にいるところまでは突き止めたんですが」と言われてしまいました(出発前のばたばたで出張届を出してませんでした)。何をやっているかは、バレバレですね。
◆といわけで、カミさんと子供2人、計3人がコタツに入ってグ~グ~寝ていて、つまらないので、つまらない記事を書いてしまいました。
大丈夫、お守り
◆こないだ夫婦で道明寺天満宮に出勤前に合格祈願に行ったのですが、早朝でまだ店開きしておらず、絵馬 とか書けなかったので、こないだの日曜日、センター試験2日目に再び行き、絵馬を書いた。その時、絵馬セットとは別に、「大丈夫」お守りというのがあり、自分の子が丈(たける)というので、これはイイということになり買い求める。こっちは、鞄に着けといてほしい。
とか書けなかったので、こないだの日曜日、センター試験2日目に再び行き、絵馬を書いた。その時、絵馬セットとは別に、「大丈夫」お守りというのがあり、自分の子が丈(たける)というので、これはイイということになり買い求める。こっちは、鞄に着けといてほしい。
◆まあ、2回目だし、ほとんど自分でやらせている。去年はもうちょっとリキ入れていたが、今年はぜんぜん。「間に合うように願書出しとけよ~」で終わり。去年は受験校の願書受付期間とか試験日とか合格発表日とか表にまとめたりしたが・・・。まあ、こんなもんで。エエ大人やし。
◆なにやら刺激を受けているのか、下の娘も勉強している姿が目に付くようになった。これまではとにかく絵を描いていた、いつ見ても。で、朝、宿題やっていないのか、ばたばたノート開いて、という姿だった。それが、このところ、帰ってくると、勉強しているではないか。偉いもんや。もちろん、今日も、十津川警部の録画を流しながらのナガラ勉強ではあるが(オレはけっしてできない)。
◆まあ、2回目だし、ほとんど自分でやらせている。去年はもうちょっとリキ入れていたが、今年はぜんぜん。「間に合うように願書出しとけよ~」で終わり。去年は受験校の願書受付期間とか試験日とか合格発表日とか表にまとめたりしたが・・・。まあ、こんなもんで。エエ大人やし。
◆なにやら刺激を受けているのか、下の娘も勉強している姿が目に付くようになった。これまではとにかく絵を描いていた、いつ見ても。で、朝、宿題やっていないのか、ばたばたノート開いて、という姿だった。それが、このところ、帰ってくると、勉強しているではないか。偉いもんや。もちろん、今日も、十津川警部の録画を流しながらのナガラ勉強ではあるが(オレはけっしてできない)。
三木市愛宕山古墳
◆先日、三木市から電話があり、前に測量した愛宕山のデータがないか、と。この測量は、科研で金があるが、 手ばかりでやる余裕なく、業者にお願いしたもの。測量業者に電話し、さがしてみたが見つからない、とのことだったが、後日、出てきたというのでデータを送ってもらった。それを三木市に送る。
手ばかりでやる余裕なく、業者にお願いしたもの。測量業者に電話し、さがしてみたが見つからない、とのことだったが、後日、出てきたというのでデータを送ってもらった。それを三木市に送る。
◆愛宕山は、その後、市の史跡になり、今回、部分的な発掘調査をしたのだという。で、オレの復元案にほぼ相当するところで葺き石が出てきたと。そうした成果を落とし込むために測量データが欲しいのだそうである。三木市でもっかい、ちゃんと測量する予定はないんですかと聞いたが、ないらしい。
◆別にデータを提供することをけちるつもりはない。ぜんぶ出した。でも、測量図としては、やっぱり業者図でいまいちなのである。ちゃんと測る必要があると。三木市の調査も計画的に確認調査を入れていくというものでもないようで、たまたまなんかもしれない。自分のところで、繰り返すが、今城塚を業者でなく高槻市は職員が測ったように、ちゃんと測るべし、と思っている。そんなん、自分でやるの、金はいらんで。土日に何度か出撃すればできるのである。
◆愛宕山は、その後、市の史跡になり、今回、部分的な発掘調査をしたのだという。で、オレの復元案にほぼ相当するところで葺き石が出てきたと。そうした成果を落とし込むために測量データが欲しいのだそうである。三木市でもっかい、ちゃんと測量する予定はないんですかと聞いたが、ないらしい。
◆別にデータを提供することをけちるつもりはない。ぜんぶ出した。でも、測量図としては、やっぱり業者図でいまいちなのである。ちゃんと測る必要があると。三木市の調査も計画的に確認調査を入れていくというものでもないようで、たまたまなんかもしれない。自分のところで、繰り返すが、今城塚を業者でなく高槻市は職員が測ったように、ちゃんと測るべし、と思っている。そんなん、自分でやるの、金はいらんで。土日に何度か出撃すればできるのである。
河内政権末期
◆やっぱり岡ミサンザイ後(前の山も?)、かなりの凋落ですね。例えば仁賢、伝統からすれば、230mくらいの 倭国王墓を築造しようとするはずですよね。が、仁賢陵がどれかはさておき、120mくらいになってしまう。即位して、王墓の築造に着手すると、やっぱり動員力が縮小していることは明々白々だったんでしょうかね。造りたくても造れない。いまの実力からすればこんなところ、という線が120mくらいということだったのでしょうか。
倭国王墓を築造しようとするはずですよね。が、仁賢陵がどれかはさておき、120mくらいになってしまう。即位して、王墓の築造に着手すると、やっぱり動員力が縮小していることは明々白々だったんでしょうかね。造りたくても造れない。いまの実力からすればこんなところ、という線が120mくらいということだったのでしょうか。
◆それはなぜかということも考えなければならない。(2)地方豪族への圧迫、(2)軍役への不満、(3)475年の漢城陥落、などが思い浮かぶが、なかなか容易ではない。
◆前にも書いたかもしれませんが、継体擁立は、たぶん武烈で断絶してとかそんなことではないでしょうね。仁賢がまだいてる間に、河内政権を見限って継体を擁立した、というのでいいんでは。オレは百済と倭の政変は連動しているとみている。示し合わせての交代劇。武寧王と継体の担ぎ出しは同根であると。隅田八幡の鏡からすると、武烈なんぞ関係なく、507年でなくその前には担ぎ出されている。要するに、ボケ山も峯が塚もぜんぶ6世紀以降ということが言えるなら、河内の倭国王とは別の担ぎ出しを証明できると思うのだが・・・。
◆それはなぜかということも考えなければならない。(2)地方豪族への圧迫、(2)軍役への不満、(3)475年の漢城陥落、などが思い浮かぶが、なかなか容易ではない。
◆前にも書いたかもしれませんが、継体擁立は、たぶん武烈で断絶してとかそんなことではないでしょうね。仁賢がまだいてる間に、河内政権を見限って継体を擁立した、というのでいいんでは。オレは百済と倭の政変は連動しているとみている。示し合わせての交代劇。武寧王と継体の担ぎ出しは同根であると。隅田八幡の鏡からすると、武烈なんぞ関係なく、507年でなくその前には担ぎ出されている。要するに、ボケ山も峯が塚もぜんぶ6世紀以降ということが言えるなら、河内の倭国王とは別の担ぎ出しを証明できると思うのだが・・・。
峯が塚の年代
◆なぜ5世紀後葉といったりするのだろうか。出土須恵器は断片だが、植野さんはMT15とする。一瀬さんもそうしている。新納さんも大刀の内容からして、そんな古くない、と言っていたようにも思う。確実に6世紀に入るものだ、ということでよかろう。かつ、市尾墓山や今城塚とほとんどかわりはない。
◆で、古市古墳群のことを考えているわけだが、岡ミサンザイのあと、ボケ山・峯が塚までの間、けっこうポッカリ空くんではないのか。埴輪で順々にならべられると、切れ目なく続いているようにも見えるが、果たしてほんとうだろうか。皆無というわけではないが、けっこう断絶的ではないのだろうか。
◆そのなかで、清寧陵と仁賢陵はあのなかにあると考えられるわけで、それがどれなんか、ということはとても重要である。むろん、ひとつひとつ考古学的な根拠を確定させていく必要があるのだが、岡ミサンザイ=雄略陵(これとて論理の整理が必要)と、今城塚=継体陵で上下を定めてみるものの、この間の配列はなかなか容易ではない。没年で言えば、雄略479(『日本書紀』)と継体527(『古事記』)で50年間もある。とはいえ、ほぼ6世紀初頭の継体擁立で世界が変わる、6世紀以降は継体政権でだいたい説明していって問題ないだろう。そうすると、5世紀末、雄略没後の20年(『古事記』では489でこれもなんでだろう・・・)、この間をどういうイメージでとらえるのがよいのだろうか。
◆で、清寧陵から考えているのだが、前の山ということはないでしょうか。ニサンザイの後継者、ニサンザイって大仙の後継者=キナシカル(的存在)で、そこそこ古い。前の山はそれを継ぐ王かとも思うのだが、それは倉西論からすると、ワカタケルの弟の清寧がいちばんふさわしいわけだ。神聖王清寧に、イチノベを殺害して執政王も允恭系が奪取してワカタケルが即位すると。清寧がいつまでいたか、考えても答などないのだが、ワカタケルと同世代と理解しておけばいいのでは。
◆埴輪だ。要するに、2次調整ヨコハケの省略の頻度で順序が決められている。『書陵部紀要』をちゃんと見る必要はあるが、前の山は墳丘の埴輪、岡ミサンザイは周堤の埴輪で比べてるのではないのか。そこあらたりで、だいたいトントンということにはならないものか。
◆白石科研の本を見直しているが、やっぱり埴輪やってはる3人で微妙に違うわけだ。共通理解に達しなくてもいいのだが、3者の相違を明示してくれるとウレシイんですけど。
◆で、古市古墳群のことを考えているわけだが、岡ミサンザイのあと、ボケ山・峯が塚までの間、けっこうポッカリ空くんではないのか。埴輪で順々にならべられると、切れ目なく続いているようにも見えるが、果たしてほんとうだろうか。皆無というわけではないが、けっこう断絶的ではないのだろうか。
◆そのなかで、清寧陵と仁賢陵はあのなかにあると考えられるわけで、それがどれなんか、ということはとても重要である。むろん、ひとつひとつ考古学的な根拠を確定させていく必要があるのだが、岡ミサンザイ=雄略陵(これとて論理の整理が必要)と、今城塚=継体陵で上下を定めてみるものの、この間の配列はなかなか容易ではない。没年で言えば、雄略479(『日本書紀』)と継体527(『古事記』)で50年間もある。とはいえ、ほぼ6世紀初頭の継体擁立で世界が変わる、6世紀以降は継体政権でだいたい説明していって問題ないだろう。そうすると、5世紀末、雄略没後の20年(『古事記』では489でこれもなんでだろう・・・)、この間をどういうイメージでとらえるのがよいのだろうか。
◆で、清寧陵から考えているのだが、前の山ということはないでしょうか。ニサンザイの後継者、ニサンザイって大仙の後継者=キナシカル(的存在)で、そこそこ古い。前の山はそれを継ぐ王かとも思うのだが、それは倉西論からすると、ワカタケルの弟の清寧がいちばんふさわしいわけだ。神聖王清寧に、イチノベを殺害して執政王も允恭系が奪取してワカタケルが即位すると。清寧がいつまでいたか、考えても答などないのだが、ワカタケルと同世代と理解しておけばいいのでは。
◆埴輪だ。要するに、2次調整ヨコハケの省略の頻度で順序が決められている。『書陵部紀要』をちゃんと見る必要はあるが、前の山は墳丘の埴輪、岡ミサンザイは周堤の埴輪で比べてるのではないのか。そこあらたりで、だいたいトントンということにはならないものか。
◆白石科研の本を見直しているが、やっぱり埴輪やってはる3人で微妙に違うわけだ。共通理解に達しなくてもいいのだが、3者の相違を明示してくれるとウレシイんですけど。
突然ですが倭王武
◆卒論提出が済み、別途、月曜〆切の仕事も終わり、ホッと一息。前から書いていたが、ちょっと2月のシン ポジウム(チラシは右)のため準備をしていて、すこしメモを書きました。どう思いますか。
ポジウム(チラシは右)のため準備をしていて、すこしメモを書きました。どう思いますか。
◆ワカタケルが、允恭後、ゴタゴタの上に即位する。『宋書』〈倭国伝〉では462年に、倭王済が死んで、世子興が献使したという。記紀の王統譜でいえば安康と雄略が考え得るが、『日本書紀』では安康末年は456年、雄略元年は457年。雄略紀には中国への2回の献使が記載され、派遣されたのは464と468年である。462年と合致しないが、百済の漢城陥落が1年ずれていることも指摘できる。世子興が献使した462年に近い時期にワカタケルが中国に使者を送っていることが確認できる。
◆そして、倭王武の上表文では王位継承がなされ、継いだ武が献使したと理解でき、それは中国に将軍号を求める倭の五王の論理となんら変わりはない。つまり478年近くに、倭王興から武への王位継承がなされていると理解できる。雄略22年(478年)の白髪立太子は、倉西の理解でいえば王位継承を示す可能性があることも示唆的である。
◆以上のように、倭王興の治世(462~478*)とワカタケル治世(書紀:457~479)はほぼ重なる。山尾は、倭王武=ワカタケル→倭王興=安康だから、安康が『日本書紀』では末年が456年になっているけれども、実際は462年までは存命していたとする。だが・・・。その後ワカタケルが王位を継承し使者を送ったと。中国への通交が実現して呉ハトリらもやってくるわけだが、それは『宋書』には記録されなかったことになる。『宋書』からすると、倭王武の献使は478年に初めて中国に行ったと考えられ、上表文で高句麗に邪魔されて使いを送れなかったという弁明とも矛盾することになる。
◆以上、倭王武はワカタケルではないということが明らかと思うのだが・・・。武=ワカタケルの絶対的根拠は、ワカタケルという実名。中国に使いを送る際の王名として、実名の意味から武の漢字一字をあてたという理解である。讃・珍・済・興がすべてそのように説明できるわけではないが、説得力はある。
◆しかし、この1点をのぞけば、倭王武がワカタケルでないことは明らかなのだが・・・
◆ところで白鳥陵=前の山=軽里大塚、これ重要ですね。岡ミサンザイのひとつ前というのは確かなんでしょうかね。同じくらいにならないか。
◆ワカタケルが、允恭後、ゴタゴタの上に即位する。『宋書』〈倭国伝〉では462年に、倭王済が死んで、世子興が献使したという。記紀の王統譜でいえば安康と雄略が考え得るが、『日本書紀』では安康末年は456年、雄略元年は457年。雄略紀には中国への2回の献使が記載され、派遣されたのは464と468年である。462年と合致しないが、百済の漢城陥落が1年ずれていることも指摘できる。世子興が献使した462年に近い時期にワカタケルが中国に使者を送っていることが確認できる。
◆そして、倭王武の上表文では王位継承がなされ、継いだ武が献使したと理解でき、それは中国に将軍号を求める倭の五王の論理となんら変わりはない。つまり478年近くに、倭王興から武への王位継承がなされていると理解できる。雄略22年(478年)の白髪立太子は、倉西の理解でいえば王位継承を示す可能性があることも示唆的である。
◆以上のように、倭王興の治世(462~478*)とワカタケル治世(書紀:457~479)はほぼ重なる。山尾は、倭王武=ワカタケル→倭王興=安康だから、安康が『日本書紀』では末年が456年になっているけれども、実際は462年までは存命していたとする。だが・・・。その後ワカタケルが王位を継承し使者を送ったと。中国への通交が実現して呉ハトリらもやってくるわけだが、それは『宋書』には記録されなかったことになる。『宋書』からすると、倭王武の献使は478年に初めて中国に行ったと考えられ、上表文で高句麗に邪魔されて使いを送れなかったという弁明とも矛盾することになる。
◆以上、倭王武はワカタケルではないということが明らかと思うのだが・・・。武=ワカタケルの絶対的根拠は、ワカタケルという実名。中国に使いを送る際の王名として、実名の意味から武の漢字一字をあてたという理解である。讃・珍・済・興がすべてそのように説明できるわけではないが、説得力はある。
◆しかし、この1点をのぞけば、倭王武がワカタケルでないことは明らかなのだが・・・
◆ところで白鳥陵=前の山=軽里大塚、これ重要ですね。岡ミサンザイのひとつ前というのは確かなんでしょうかね。同じくらいにならないか。
プラグイン
カレンダー
カテゴリー
フリーエリア
最新コメント
最新記事
(07/10)
(07/10)
(07/10)
(07/10)
(07/10)
最新トラックバック
プロフィール
HN:
雲楽
年齢:
61
性別:
男性
誕生日:
1964/03/22
職業:
大学教員
自己紹介:
兵庫県加古川市生まれ。高校時代に考古学を志す。京都大学に学び、その後、奈良国立文化財研究所勤務。文化庁記念物課を経て、現在、大阪の大学教員やってます。血液型A型。大阪府柏原市在住。